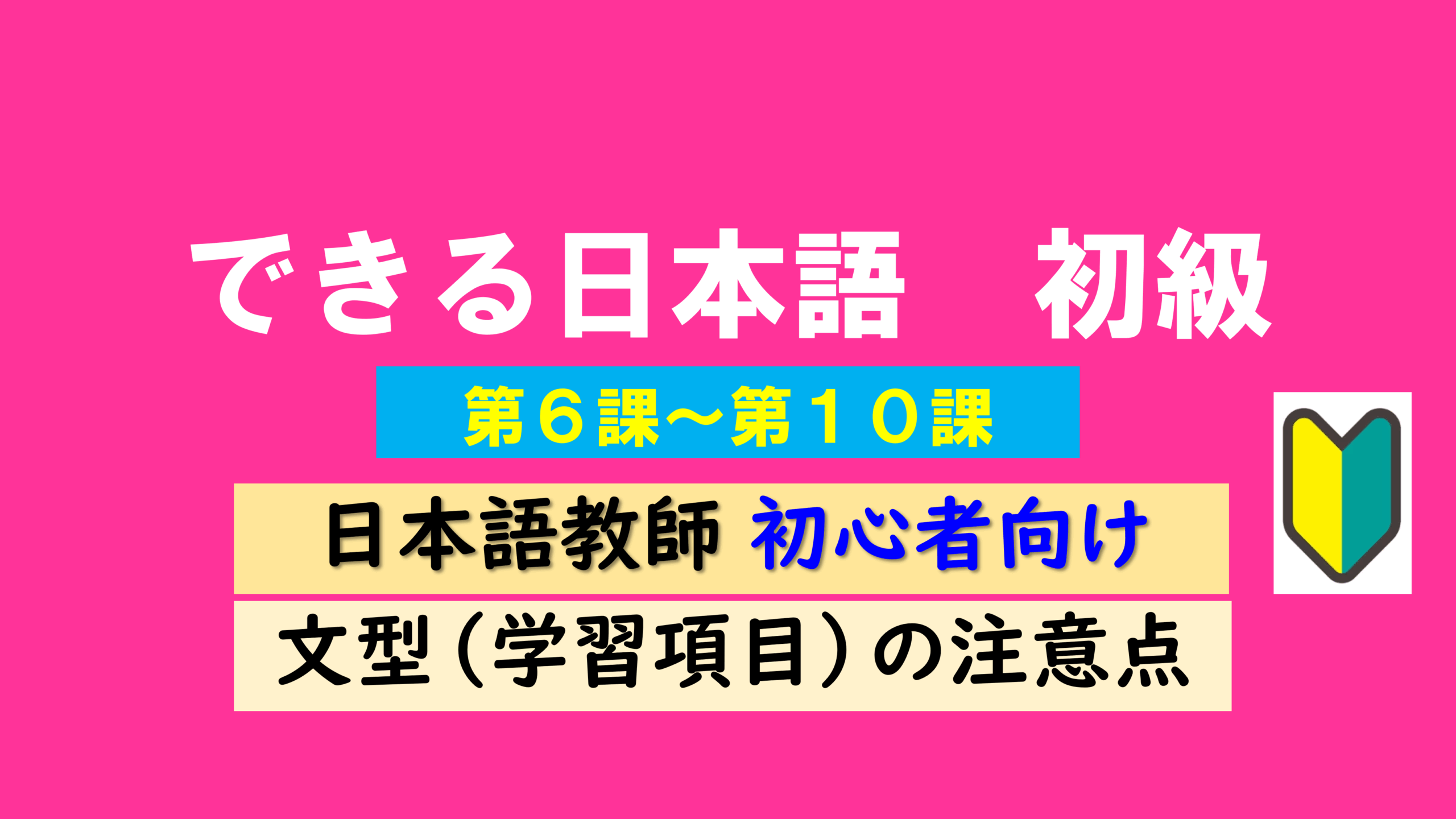■第6課~第10課の文型の注意ポイント(導入する順番に情報を掲載しています)
➀ 【V】ませんか
[テキスト]
・第6課①で、相手を誘うときに使う文型として導入します。
[注意ポイント]
・『【V】ましょうか』が、初中級の第6課①に出てきます。
※学生によっては違いを質問してきますが、全体での説明はしない
(例)〈第6課①〉 今晩、一緒に映画を見ませんか。
(例)〈初中級第6課①〉 どこへ行きましょうか。 ※相手にアイデアを聞きます
② 【N1(場所)】で【N2】があります
[テキスト]
・第6課①で、場所を表す「で」を導入します。
[注意ポイント]
・第4課②で、既に導入した『【N1(場所)】に【N2】があります。』をここで復習すること。
・「~に」と「~で」の違いを、例文を使って詳しく説明することで2つの文型を理解させる。
・今回の『【N1(場所)】で』の『で』は、「その場で」何がある/することを言うときに使います。
・第4課②の『【N1(場所)に】の『に』は、「どこにあるか」の「に」です。
(例文)今晩、大阪で野球の試合があります。 ※その場所「で」行う(動作)
(例文)私の町にきれいな川があります。 ※存在の「に」
・まだ初級の6課ですので、「に」を使う存在の動詞(いる・ある・住むなど)移動や方向の動詞(行 く、くる、入るなど)は、今後導入していきます。間違えやすい助詞ですのでたくさん練習し理解させることが必要です。
③ ~ね (確認)
[テキスト]
・第6課③で、話し相手への【確認】の「ね」として導入する。
[注意ポイント]
・第4課③で導入した【共感】の「ね」を復習し、2つの文型の違い、使い分けに注意させること。
(例文)(※相手に対して言います) 明日は5時でしたね。 ※確認
(例文)(※相手に言います) 暑いですね。 ※共感
④ ~よ
[テキスト]
・第6課③で、相手に対して【情報提供】(教えます)としての「よ」を導入します。
[注意ポイント]
・すでに文末にくる「ね」を導入しているので、ここでは【情報提供】(教えます)の「よ」として、しっかり例文を示して理解させること。「よ」がある場合とない場合の文の違いなど含め。
(例文)この本は、とてもおもしろいですよ。
⑤ 【Vテ形】ください ※動詞のテ形の初導入 (指示・依頼)
[テキスト]
・第7課②で、初めて【動詞のテ形】が『【Vテ形】ください』で導入されます。
[注意ポイント]
いうまでもなく、【動詞のテ形】は、様々な使い方と意味があります。日本語教師として初心者のことは、【動詞のテ形】の意味の広さと、できる日本語で導入される課も分散されているため、理解するのが難しかった。それで、体系的に整理し、自ら理解しないと授業中、混乱してしまいます。ここでは、文型の意味の説明には、学習者には未習語彙になりますが、日本語教師として意味を理解するためです。当然、学生への導入時の意味などは、簡単な言葉に置き換えながら、「先生に言うときには使いません。/使えます。」など表現を変えて説明し、ゆっくり理解させていきましょう。
(例文) 私の飲み物を取ってください。 ※指示・依頼
⑥ 【Vテ形】います (進行・継続)/(職業)
[テキスト]
・第7課③と第8課①で、『【Vテ形】います』が導入されます。
[注意ポイント]
・意味としては、【進行・継続】/【職業】として、私の場合は区分けしています。
・今後、『【Vテ形】います』は他にもたくさんの意味があります。
第8課、第11課、第13課、第15課に分かれて導入されていきますので注意してください。
(例文)〈第7課③〉 山田さんはあそこで電話をかけています。 (進行・継続)
(例文)〈第8課①〉 私は大阪に住んでいます。 (進行・継続)
(例文)〈第8課①〉 私は日本語学校で日本語を教えています。 (職業)
⑦ 【イ形容詞】くて、~ / 【ナ形容詞】・【名詞】で、~ (並列)
[テキスト]
・第8課②で、形容詞、名詞を並列する表現として導入します。
[注意ポイント]
・【イ形容詞の場合】は「~くて~」。【ナ形容詞・名詞の場合】は「~で~」になる。
・並列を意味する文型ですので、前件、後件のバランスには注意しましょう。
(例文) 山田さんは目が大きくて、髪が短いです。
山田さんはまじめで、親切です。
弟は10歳で、小学生です。
⑧ 【V辞書形】 ※【動詞の辞書形】の初導入
[テキスト]
・第9課①で初めて【動詞の辞書形】が、『【V辞書形】こと』で導入されます。
[注意ポイント]
・【動詞の辞書形】は、「食べる」、「飲む」など、単独で意味が通じる場合が多いので、初級の学生が質問に答える場合に、「辞書形」だけで答えようとすることが増える場合もあるので注意してください。
(例文)〈第9課①〉 私の趣味は映画を見ることです。 【V辞書形】こと
〈第9課②〉 私は料理を作ることができます。 【V辞書形】ことができます
※【注意】学生によっては、「~できます。」を使わずに、【可能形】を使う学生もいますので、【可能形】は、初中級の第1課で勉強することを把握しておきましょう。
⑨ でも
[テキスト]
・第9課①で「(A)。でも、(B)」を導入します。
[注意ポイント]
・上記(A)と(B)の関係は、必ず(A)と(B)が異なる関係であること。
・(A)が(+)なら、(B)は(-)。また、(A)が(-)なら、(B)は(+)になること。
・第4課②の「~が、から」との違いを説明すること。意味は同じ逆接です。
(例文)〈第4課②〉 私の家は大きくないが、きれいです。
※一文にする/書き言葉・フォーマル
(例文)〈第9課①〉 私の趣味はスポーツです。でも、最近全然していません。
※二つの文に分ける/話し言葉・カジュアル
⑩ 【Vナイ形】でください ※【動詞のナイ形】の初導入
[テキスト]
・第10課②で「【Vナイ形】でください」で、初めて【動詞のナイ形】を導入します。
[注意ポイント]
・この表現を使う場合、知らない人などには使わないように注意してください。
・注意の場合と指示の場合があります。答える言い方に注意させてください。
(例文1) だめですよ。この会場では、品物に触らないでください。〈注意〉
(言われた時)「すみません。」
(例文2) すみませんが、この会場では、品物を触らないでください。〈指示〉
(言われた時)「わかりました。」
■学習項目の順番に上記内容をまとめています。(テキストP270~)
注意点などを色を変えて追記しています
■参考図書コーナー
★日本語教員試験対策本 ※周りの人から評価高いです!