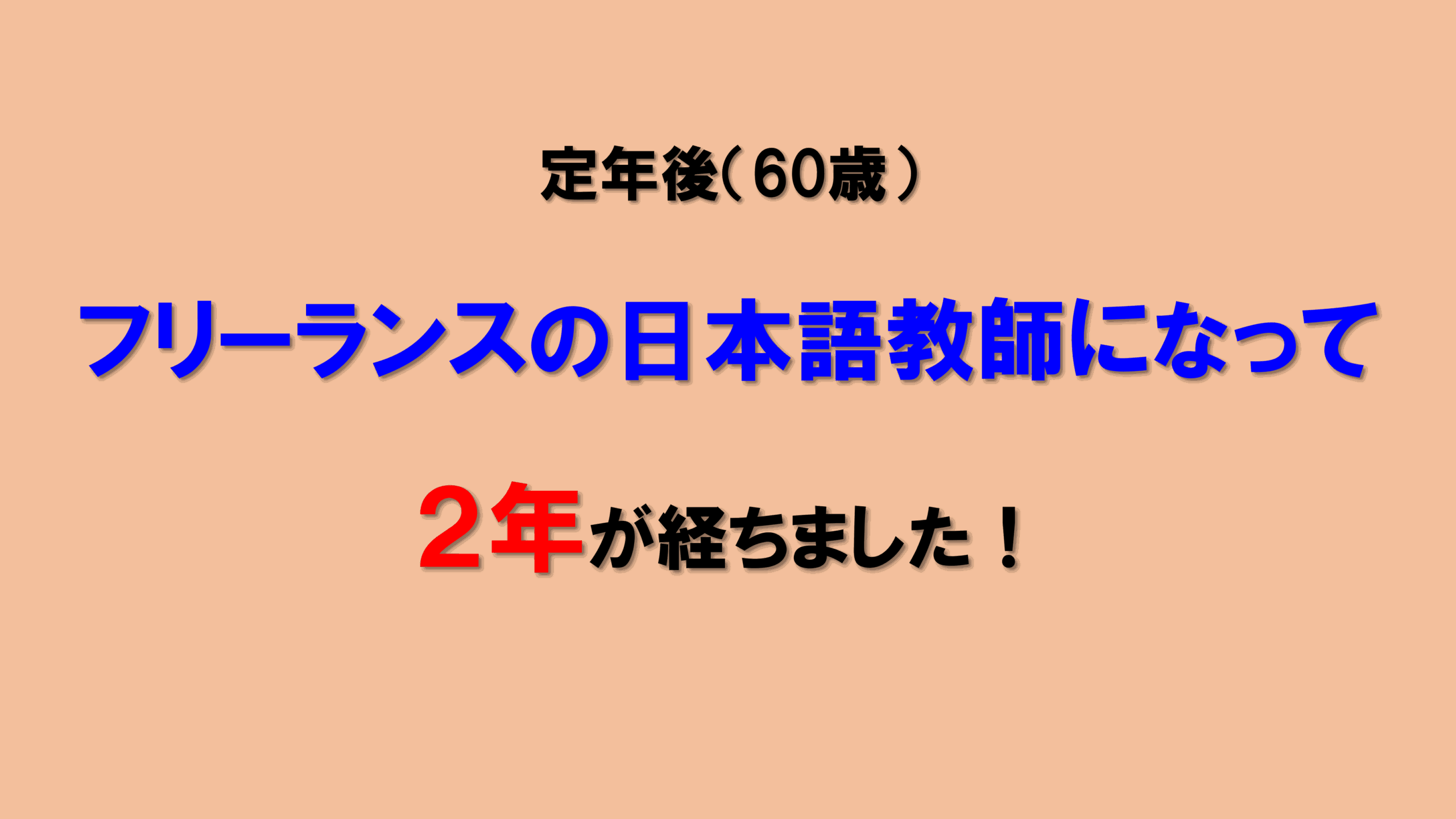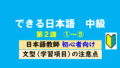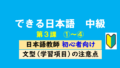週2日ペースで約2年間、日本語学校で仕事をさせていただきました。「できる日本語(初級)」(赤色)からスタートし、気がつけば「できる日本語(初中級)」(黄色)、そして「できる日本語(中級)」(青色)の第14課までを担当させていただきました。自分にとっては幸いにも少しずつ教科書のレベルをアップしながら取り組むことができたのは、本当に良かったと思っています。この経験で気づいたことなどを中心に、ブログを書かせていただきます。
是非、あたたかい目でご一読いただければ幸いです。これから日本語教師を始められる方、そして、始めたばかりの新人の先生方の参考になれば幸いです。また、同世代の先生方とも色々なことを共感できれば嬉しいです。
日本語教師としての2年間を振り返り感じたこと
(1) 初級段階での教育が後々影響してくることを実感
日本語教師を始めたときは、初級を担当し、本当に授業準備に忙殺され、自分の授業をこなすので精一杯であったことを今でも鮮明に覚えています。当時のベテランの先生から、「この初級の段階が最も大事で、基本文型や助詞の使い方、動詞の活用をしっかり教えないと、定着させないと、後々レベルアップしたとしても、誤用がなかなか直らない。」と言われていました。その時も頭の中では理解し授業中もしっかり取り組んできたつもりでしたが、中級レベルの学生の会話や発表を聞くと、そのことを強く再認識するようになりました。つまり、話せることは話せるが、聞いていて「何か…ぎこちない感じ」がしていました。文型や語彙のテストなど優秀な学生でも、やはり話すとなると気になるところがあります。当時のベテランの先生が言われていた通り、初級段階での取り組みが本当に重要だと強く実感しました。
10月から、初級のクラスを担当もすることになったので、1年前の授業の内容を見直し、正しい文型の使い方、適切な語彙の使い方、そして助詞の使い方などに注力し、今後できるだけ誤用を減らせるような授業を考えたいと思っています。
(2) 目的・目標をよく理解した授業内容にするためにもテキストなどを深く読み込む
毎回授業を考える際に、日本語学校の方針はもとより、使用するテキスト(私の場合は「できる日本語」)の各課における「行動目標」、「できること」を理解するだけでなく、その内容を確認するためにも、テキストの内容を深く読み込み、「どこで、何を、どうする(どうさせる)」などを考え授業を構成するようにしなければなりません。これも、分かっているつもりでしたが、今、テキストを読む返すたびに、「ここにその意図があったのか…」と、恥ずかしながら、今更気づくことがあります。やはり、まだまだテキストが深く読み込めていないことを実感しています。また、日本語学校で作成されている評価項目(会話テスト、発表テスト、作文テストなど)も理解し、テキストとの関係を見出し、授業ではそのポイントを押えた授業をしていきたいと考えています。
(3) 授業をテンポよくスムーズに進めるためにも早期に学生の名前をマスターする
レベルが上がるにつれて学生を巻込んだ授業が必要になります。つまり、先生が説明するのではなく、学生にこれまで学んだことを思い出させ、考えさせることが求められるからです。一人の学生に聞くのではなく、その周りの学生にも広げながら、みんなで考えるような授業が求められます。その時、どうしても学生の名前が必要になります。日本語学校には座席表があり、学生の名前(ニックネーム)が準備されていますが、それを見ながらだと、どうしても「間」ができてしまい、ついつい私が話してしまう傾向になりがちでした。週に2日、別のクラスなので学生の名前を覚えるのは、私にとっては苦手でしたが、当たり前ですが、学生の顔と名前は早々に覚え込み、スムーズな授業ができるようにしていきたいです。スムーズな授業が学生の理解を促し、退屈な授業ではなく、常にいい意味で緊張感のある授業ができるからだと思います。
まとめ
やはり経験することで自分に足りない事も更に明らかになりますが、各レベルを体験することで見えなかったことが見えてきた気もします。やはり、「何事も経験」ですね。10月からはこれまで週2日でしたが、週3日にチャレンジします。100点満点の授業はできませんが、悔いのない、後悔しない授業をするためものこれまで書いたことを意識して授業準備をし、私の授業を聞いてくれる学生が少しでも楽しく日本語能力が向上するように今後も頑張っていきたいです。是非、みなさん今後ともよろしくお願いします。一緒に頑張りましょう!
【私が使っている参考図書シリーズ】 ※Amazonのリンクが貼ってあります
★日本語教員試験(応用試験)対策本 25年9月末時点での最新号です!