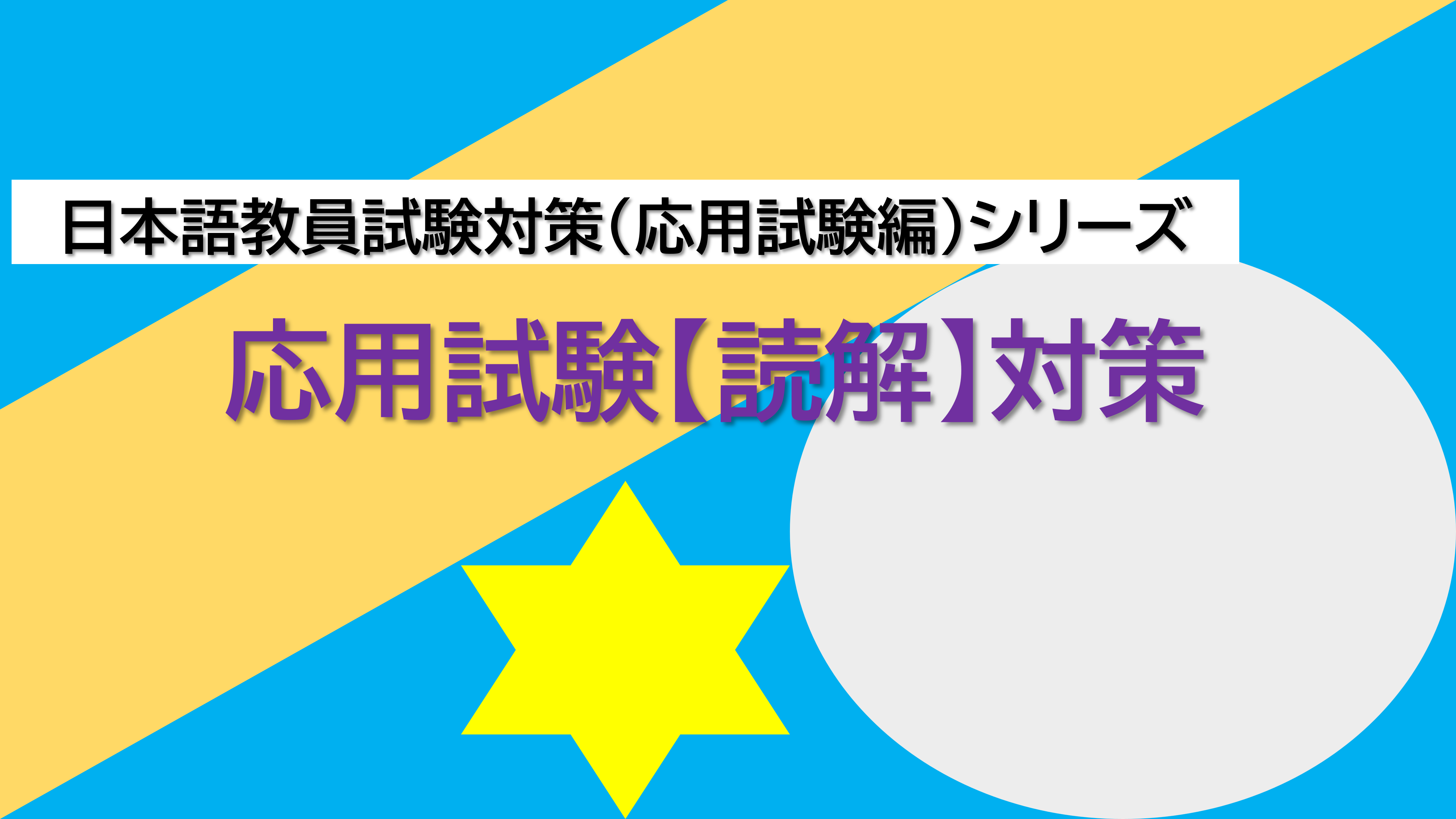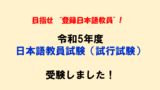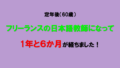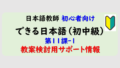日本語教員試験 応用試験(読解)対策の内容をまとめました!
はじめに
登録日本語教員試験の応用試験には、「聴解試験」と「読解試験」があります。その点数と時間の配分は、「聴解試験」が50分で50問であり、「読解試験」が、100分で60問である。合格基準は、「聴解試験」と「読解試験」の総合計の6割である。実際は1問1点なので、総合計110点の6割、つまり、66点以上であれば合格です。これは、「聴解試験」、「読解試験」に足きり点がないため、私のように「聴解」が苦手な場合、「聴解試験」に失敗しても「読解試験」で挽回できる内容になっています。つまり、コツコツ勉強すれば必ず道は開ける試験と私は思っています。そのためにも、試験対策をしっかりすることはとても重要です。今回は、「聴解試験対策」に続く、「読解試験対策」を私の経験(令和5年度の試行試験と令和6年度の試験)から、あらためて整理しまとめてみました。みなさんの応用試験対策に役立てていただければ幸いです。
これまでの応用試験(読解)内容に関する情報ついて
登録日本語教員試験の実績としては、令和5年度に実施した試行試験と、昨年初めて実施された令和6年度の日本語教員試験が開催されただけです。また、試行試験含め昨年度の試験問題は、日本語教育能力検定試験とは異なり、試験問題を持ち帰ることができないため、どんな試験だったのかは、受験された方々の記憶を基に内容をお伝えしたり、一部、文化庁のホームページで公開されている「サンプル問題」を参考にするぐらいです。また、現時点(25年3月)で、登録日本語教員試験対策として出版されている本は下記に記載している本ぐらいと思います。今年の5月に販売予定として応用試験対策本があります。まだまだ少ないのが現状です。そこで、私がおすすめしたい本は、文法だけではなくしっかり用語の意味、その背景も学べる本です。通称『赤本』と呼ばれていますが、正式名称は『日本語教育能力検定試験 完全攻略ガイド』です。とてもわたりわかりやすく解説されていますので、私のおすすめ本の一つです。
【文化庁のホームページ】より
★「1資料4 日本語教員試験試行試験 結果の概要 文化庁」より
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/nihongo/nihongo_124/pdf/94009301_03.pdf
※応用試験2(読解)のサンプル問題は、P17から参照ください
【私の過去のブログ記事】より
①令和6年度「日本語教員試験」受けました!(速報)
※試験③ 応用問題Ⅱ(読解)の試験内容 (順不同)※記憶より
②令和5年度 日本語教員試験(試行試験)受けました!
※試験②(応用試験Ⅱ(文章問題))について
【現在の参考図書】※Amazonのリンク張っています
- 日本語教員試験 対応用語集[学習アプリ対応]
- 日本語教員試験 まるわかりガイド[音声DL付]
- 日本語教育能力検定試験 完全攻略ガイド
- 令和5年度 日本語教育能力検定試験 試験問題
- 令和6年度 日本語教育能力検定試験 試験問題 (発売中)
★令和7年5月時点での最新版「日本語教員試験(応用試験)」対策本です!
応用試験(読解)の対策について
(その1)「日本語教育能力検定試験〈試験Ⅲ〉」の過去問対策について
「読解試験」対策について、現在までに公開されている情報や市販されている参考図書だけでは難しく、日本語教育能力検定試験〈試験Ⅲ〉を活用した対策が大切ではないかと思います。私の場合ですが、過去5年分の日本語教育能力検定試験を令和元年度から令和5年度の5年分を『過去問』として準備し対策をしてきました。しかし、『過去問』には解説がないため、過去問解説で有名な先生方のブログ記事を参考にしながら理解を深めていきました。その際、大変、お世話になった先生方のブログを紹介させていただきます。わからない問題、間違えた問題に関しては、本当に丁寧に解説されているので、その内容を読むことで理解を深めることができました。
●【日本語教育ナビ】より
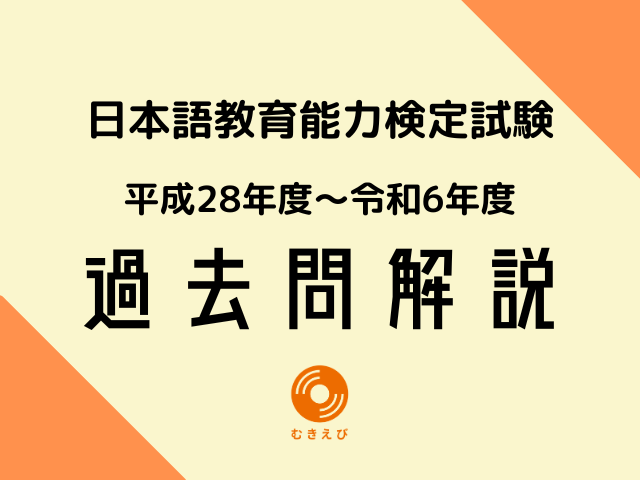
※日本語教育能力検定試験 過去問 解答解説
●【毎日のんびり日本語教師】より
※日本語教育能力検定試験 過去問解説
(その2)有名なYouTubeの先生の動画より対策勉強を強化
日本語教育能力検定試験の過去問を勉強しても、本当にその知識が定着しているか不安になります。私は、ある程度、過去問の勉強が済んだら、その知識が定着したかを確認する意味でも、下記の有名なYouTubeの先生が作成された動画を見て、瞬時にその質問に対応できるか含め拝聴させていただきました。また、動画ですので限られた時間、しっかり対策勉強することもできました。また、その先生方の動画を「全部見る!」と強い意志を持つことで継続した勉強にも繋がりました。大変、お世話になりました先生方のYouTubeを紹介させていただきます。言うまでもありませんが、数多くの動画を発信されており、日本語講師になるために必要な情報も沢山あります。
●【研究 日本語教育能力検定試験】 大根先生
●【こせんだ式日本語教室】 こせんだ先生
(その3)私の経験からの重要なポイント(まとめ)
応用試験(読解)対策として、最後に、私なりに重要なキーワードをまとめてみました。また、これらの知識は日本語教師としても必要な知識ですのでしっかり学習しましょう!
■【日本語教育の参照枠】の概要はしっかりマスターしましょう!
文化庁のホームページからでも検索できます。一通りの内容は理解しておきましょう。全体的な尺度(A1~C2)、5つの言語活動などしっかり内容を理解しましょう。尺度などは、日本語学校でもよく使われる用語です。
「日本語教育の参照枠」 文化庁のHPより
《注意》 下記【 】の用語は、『日本語教育能力検定試験 完全攻略ガイド』より
■【言語教育法・実技】
・特に教授法(タスク中心の教授法など)の用語、内容は理解しておきましょう。実際の現場でも活用できる知識です。
・「書く技能の指導」など「作文」指導に関する内容(初級・中級レベルでの)を理解しておきましょう。「作文指導」の用語でも説明されています
■【評価】
・評価の分類と評価方法などの理解、テストにおける評価などの内容をしっかり理解する必要があります。令和6年度は、偏差値である「Z値」などの用語も出題されています。テストの点数に関する評価の用語も重要です。
・「診断的評価」、「形成的評価」、「総括的評価」などの違いや内容は理解しておきましょう。多くの日本語学校でも実施されているテストが当てはまります。小テストや単元テストはどれに該当しますか?(形成的評価です)
■【言語教育と情報】
・eラーニングなどオンライン授業に関する知識や同期、非同期型など理解しておきましょう。実際に日本語教育の現場でもオンライン授業もコロナのころ多くの学校で取り組まれていました。
・「著作権」に関してはよく出る用語です。実際の日本語学校でも教材を作る際には注意すべき内容ですのでしっかり理解しておきましょう。何が「著作権法違反か?」など過去問にもよく出題されています。
■【言語習得・発達】
・フォーカス・オン・フォームズ、フォーカス・オン・ミーニングフォーカス・オン・フォームの用語の理解と教授法との関連は整理して理解しておきましょう。
・インプット仮説、アウトプット仮説の内容と違いなどはしっかり整理し理解しましょう。
【言語習得・心理】
・コミュニケーションにおける意味交渉(明確化要求、確認チェック、理解チェック)に関する用語の理解など
【その他】
・実際の現場(日本語学校)を想定した問題として、ベテラン先生と新人先生のやり取りを通じた問題などもあり、覚える問題ではなく、考える問題もあります。そういう意味では応用試験(読解)は、現役の先生としては解きやすい問題だと感じました。
・言うまでもありませんが、「日本語文法」に関する内容はしっかり理解しておいてください。私は今も勉強中です。
【私が使っている参考図書(試験対策用)】 ※Amazonのリンクを貼っています
【登録日本語教員試験対策本(新刊情報)】25年9月末発売予定
【登録日本語教員試験対策本(新刊情報)】25年6月末発売予定
まとめ
令和7年度の試験は11月2日(日)です。是非、合格目指して頑張ってください。応用試験だけの受験であれば、勉強した成果は必ず出ます。留学生の推移や国の問題などは基礎試験と思われます。また、歴史上の人物も出ませんでしたので、今後、日本語教師として活動していくために必要な知識に絞って取り組むこともできます。大変とは思いますが、Youtubeの動画なども活用しながら学習を続けて下さい。応援しています。また、このブログが少しでも役に立てたなら幸いです。今後ともよろしくお願いします。